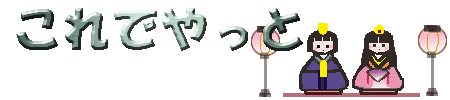
*** 匿名投稿 ***
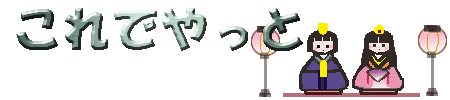
*** 匿名投稿 ***
2003年11月
|
原作中の実名は全て仮名に変更しました(HP担当)
阿佐ヶ谷を離れて数年経っていたが、久しぶりに網代木で会おうと決めた。宮野夫妻と私、奈々子の四人だ。奈々子は宮野とは何度か会っていたが、千夏さんとは初めてだ。 最初少し緊張気味だったが、すぐに慣れた女たちは私と宮野の悪口を交えながら、親しげに話している。客あしらいが一段落すると浅田さんも座り込み、若い二人を笑わせる。浅田さんは粗い格子縞の着物に、少し長めに伸ばした髪を無造作に後ろでアップにまとめ、もうすっかり小料理屋の女将の格好が板についていた。『涼』の時代とはずいぶん印象が違う。思えば私たちはこの人の前に様々な醜態を晒してきた。板前のみっちゃんも懐かしそうに挨拶に来て、「お祝いだから」と特別にサービスしてくれた。千夏さんはもうすっかり宮野の操縦法を身に着けたようで、飲み過ぎないように監視の目を離さない。 「ハヤトさんったら、最初のとき随分変なこと言うんですよ」と千夏さんがおかしそうに奈々子に話しかける。「アルバイトに雇われたのかって。」私も思い出した。 花が咲いている、と思ったのは嘘ではない。 西千葉駅に宮野がいたが、隣に立っているのは花ではなく女性だった。色白の顔の上には麦藁帽子が載っていて、長い髪が風に揺れている。襞々の、胸まである長いスカート(教養がないとこういうとき困る。たぶん一般的な名称があるのだろう。アルプスの少女ハイジのようだと私は思った)に編み上げのサンダルを履き、小さなバスケットを持っていた。 「これ、チナツ」と宮野が紹介する。なんだ、冗談か。随分手の込んだ仕掛けを考えたものだ。この一年ほど前から、私たちはちょっとした賭けをしている。私を驚かせて賭け金をふんだくろうと、モデルか何かに頼んで一緒に来てもらったに違いない。日当をいくら払うのだろうか。 「どうして、そう思うんですか?」と彼女が小首を傾げる。だって、あなたのような美人がついているのは信じがたい。「でも、そうなんですよね。」白い顔がぱっと綻ぶ。可憐だと私は思った。 「二人で内房の海さ行く積りでよ。」時間があるからちょっと寄ったと宮野が言う。宮野の持っている紙袋にはタオルが見える。この当時、私は千葉営業所に移っており、西千葉駅から十五分ほどのところに部屋を借りていたのだ。 結局海に行くのはやめ、「飲もうぜ」というのはいつものことだ。海は口実で、私に彼女を紹介するのが目的だったのだ。私の反応が良かったので安心したのだろう。何年も前に、宮野がSという女を『涼』に連れてきたときには、私は一切口も利かなかった。そのせいでもあるまいが、その女と宮野はすぐに別れた。 千夏はさんは働きながら大学に通っている。児童書専門の出版社だから専攻にちょうど合う。児童文学が好きな女性は真面目なものと相場が決まっている。宮野はいずれ秋田に戻るための修行として、その会社に入って彼女と知り合った。地方まわりの多い仕事で、出張になると一週間は戻ってこない。時には会社を休ませて、出張先に彼女を呼び寄せたこともあるそうだ。 卒業したら結婚すると、彼女ははっきりと言った。私は先を越されたことをようやく理解したが、それほど悔しくはなかった。「いや、親父さんが酒飲めね人でよ。参ったよ」。謹厳な教師で一滴も酒を飲めない父親の前に座って、宮野がどう挨拶したかを想像すると少しおかしい。宮野は愚痴をこぼすが、それでも宮野のために酒を用意してくれたと言うのだから、気に入られたに違いない。 「ハヤトさんのライフワークは何ですか?」真剣な目だ。いったい私のことをどう説明しているのだろう。宮野がニヤニヤしている。私にはやるべき何の目標もない、とは言いかねた。「俺たちはね、昭和の歌謡史をやってるの」「んだ、昭和歌謡史が俺がたのライフワーク」と宮野も合わせる。 古い歌謡曲を歌い、二人で繰り返してきた弥次喜多道中の数々を数え上げると、彼女はそのたびに笑った。空になったウィスキーの壜にタバコの煙をいっぱいに吹きいれ、よく振って火をつけると、白い煙が壜の中で一瞬青白い炎をあげて燃え上がる。こんな詰まらないことにも、本当に驚いて笑い転げた。 「しかし」と私は尋ねた。勢多郡富士見村で赤城山を見上げながら育った彼女が、秋田についてきてくれるのだろうか。「私、大丈夫です」ときっぱりした返事が返ってきた。 「ナナコさんは、どうしてハヤトさんと?」 私たちには特別なことはない。奈々子は短大の英文科を出てすぐに千葉営業所に入社してきた。全く無能だった私も、その頃には係長に昇進していた。苦労したが車の免許もとり、ようやく少しは仕事に慣れてきたようだ。奈々子と一緒に男の新入社員も入ってきたから、先輩らしく振舞わねばならぬという意識も働いていた。 仕事で英文タイプが必要だと分かったとき、専門のタイピストではないのだから別にそんなにムキになる必要はないのだが、奈々子は夜タイプ学校に通って一級をとった。着付けにも挑戦して資格をとった。私とは大分、気合の入れ方が違う。大晦日、私たち男の社員は四時頃から飲み始めていたが、営業マンの整理が悪いため入金の明細がなかなか締められず、奈々子だけが十時頃までかかってしまったときは、トイレでこっそり泣いていたことも、私は知っている。 小さな営業所で、私と三歳しか違わない所長が、部下を集めて騒ぐのが好きな人だったから、飲む機会が多かった。「おナナ」と呼ばれるようになった奈々子も誘われ、一緒になる回数が増え、そのうちなんとなく、遅くなったときは私が家まで送って行く暗黙のルールが出来上がった。そのことに誰も不審を感じないようになった頃、私はプロポーズした。奈々子はひっそりと泣いた。 まだ年齢的に早すぎるのではないかと奈々子の父が少し難色を示し、一年ほどは待たなければならなかったが、就職して丸二年になる来年の三月で退職し、四月の末に式を挙げることに決まった。義父は自分が二十一歳で結婚し、二十二のときには奈々子が生まれていたことなどすっかり忘れた振りをしている。娘ばかり三人も抱えた父親は、最初の娘をすぐに手放したくないだけだった。それを考えると、千夏さんの父親はよく簡単に許したものだと思う。二人だけの姉妹の上の方はまだ独身で、宮野が挨拶に行ったときには千夏さんはまだ学生だったのだ。 私も長男だから、奈々子の母は最初心配だったらしい。二人とも下関市彦島の出身で、義父は三井系列の会社のエンジニアだったが、事業所の閉鎖に伴い、会社の斡旋で下関から千葉の関連会社に移ってきた。奈々子が小学生の頃だ。なにしろ日光より北には行ったことのない人たちだから、娘が攫われてしまうのではないかと、恐れたようだった。 「秋田っちゃ遠かろうね。」下関弁が全く抜けない義母にとっては、地の果ての蝦夷の住む国くらいにしか思えなかったのだろう。両親は既に関東に住んでいること、私自身も転勤はあるが、別に秋田に帰る積もりもないことが分かり、漸く安心した様子だった。数年後にまさか秋田に転勤になろうとは、そのときは夢にも思わない。 私の親は喜んだ。昔から、私がいなくても宮野は時々私の実家に顔を出していたが、結婚してからは夫婦で顔を出すようになっていた。父は「二番目の息子」と呼んで可愛がっていたから、なおさら第一の息子の不甲斐なさに、口には出さなかったが不満を感じていたことは間違いない。初めて奈々子を引き合わせたときには芯からほっとした様子で喜んだ。母も奈々子を気に入った。 特別なデートなどしたこともなく、赤提灯か縄暖簾の居酒屋が、会社以外で私たちの会う場所だった。躾の厳しい両親の元では羽目をはずすこともできにくい。実家を離れて東京で暮らしていた宮野たちとは随分違う。奈々子の数少ない冒険といえば、親には嘘をついて私と鎌倉に一泊で遊びに行ったことと、夏休みに示し合わせて北陸に旅行したことくらいだろう。 「あたしさ、あんたたち、ホントどうなるんだろうって心配してたよ」浅田さんが嬉しそうに言う。「ミヤノもハヤトも、ホントに良い人見つけたね。もう大丈夫さ。」私たちだけではない。浅田さん自身もみっちゃんと一緒になることに決めていた。佐藤光男は私たちと同い年で浅田さんとは随分歳が離れているが、腕の良い優しい男だ。 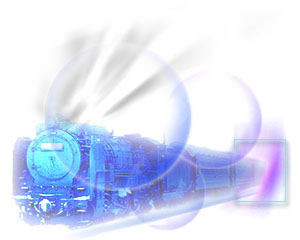 「これでやっと」と宮野が柄にもなくしみじみと言う。そうなのだと私も思う。迷いに迷った挙句の果て、散々繰り広げた私たちの愚行ももう卒業する時だ。長かったひとつの季節が漸く終わったことを私は感じていた。
「これでやっと」と宮野が柄にもなくしみじみと言う。そうなのだと私も思う。迷いに迷った挙句の果て、散々繰り広げた私たちの愚行ももう卒業する時だ。長かったひとつの季節が漸く終わったことを私は感じていた。その後長男が生まれて一年ほど経った頃、私は秋田営業所長としての赴任が決まった。たまたま営業部門に秋田出身者は私ひとりだったというのが、選任された理由だ。羽田空港に見送りに来た義母は、今生の別れかと思うほど泣いた。 追っかけるように、宮野も念願かなって秋田に戻り、父親と一緒に小さな店を開いた。外商に力を入れる方針だから、店舗は小さくても良いのだ。児童書に力点を置いた品揃えは、明らかに妻の影響だろう。 |