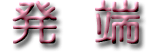
*** 匿名投稿 ***
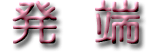
*** 匿名投稿 ***
2003年9月
|
原作中の実名は全て仮名に変更しました(HP担当)
「あれが全ての始まりだった。」 記者に届けられた手記はこの一行から始まる。物語中「私」で表記される主人公は、古くからの友人である記者に何事かを託したかったのかと思われるが、それが何かについては分明でない。公表を希望するらしい主人公に代わって、原稿用紙に乱雑に走り書きされた文字を読み取り、こうしてワープロに載せる作業は簡単ではなかった。どうしても判読できない人名はやむを得ず記号で表した。この作業に対して主人公は何の謝礼も用意していない。少し配慮というものがあっても良いのではないだろうか。主人公の吝嗇な性格が現れている。 主人公は、これは自伝だと語っているが、作業が進行するにつれ、記者には、主人公の語る内容がにわかには信じられないようになってきた。状況設定が不自然だし、話の展開も安易というより、なにか主人公の自虐に都合の良いように動いているように思われる。「私は」「私の」としつこい位自分を強調する文体は自意識の過剰を表現しているようで、自己卑下と反省を装う陰に傲慢な居直りも透けて見える。ただ、いささかは掬すべき真情が垣間見えるように思える箇所もある。友人である故の感傷だろうか。 なにはともあれ、記者としては主人公の報告をできるだけ正確に採録することだけを心掛けた。当初は、酷く不自然な展開や主人公の独りよがりが感じられる点について、記者の評を注釈の形で挿入し、読者の便に供そうとも考えたが、取り掛かってみるとこれも余りに煩瑣であり、一切放擲した。本文と注釈とがほとんど同じ位の分量になりそうだったからだ。これら一連の物語がはたして真実であるか、あるいは主人公の捏造もしくは妄想の産物であるかは、読者の判定に委ねたい。 「あれが全ての始まりだった。」 弘幸と約束して紀伊國屋の前で待っていたが、なかなかやって来ない。この男はいつもそうだ。大学に入ったばかりで、東京の地理にもまだ慣れていない私たちは、新宿なら紀伊國屋と決めていた。三十分も待った頃、すぐ傍で、やはりなかなか来ないらしい相手を待っている女と目があった。お互いにうんざりしている様子が分かるので、なんとなくニヤッとしながら会釈を交わした。「女の子?」とその女が話しかけてきた。いや、男だよと私が答えると、彼女は「あたしの方は女、イヤになっちゃうよね」と言う。それからも二十分ほど待っていたが相手は来ない。あと十分待って来なかったら二人でどっか行っちゃおうか、そうしようと答えているところに、女の相手が現れた。「何かの縁だから、連絡頂戴」と女は電話番号を書いたメモをくれた。 弘幸が来たのはそれから更に五分後で、私はもう頭にきていたから口も利かずに歩き始めた。「すまん、すまん」と弘幸が詫び、それなら今日はお前の奢りだと話を決めてそのまま酒場を探した。 私が女に連絡したのは六月に入ってからだった。指定された吉祥寺の駅前に行くと、女の横に男がいた。予備校で一緒だったDだと紹介されたが、その男は仏頂面を崩さない。随分、愛想のない男だと思ったが、迂闊なことに私はその男が私に嫉妬しているのだということに気づかなかった。女は地方の女子高を出て、今は女子大の国文科にいるのだそうだ。一浪したというから私より一つ年上だということが分かった。 「迂闊」というも愚かではないかとは、後で考えた智恵だ。むしろ、うっかり電話番号を教えてしまったが、後悔した女が用心のために男を連れてきたと考えるほうが自然だと思われる。とすれば当然、その男は女の恋人であろうか。しかし、その当時の私は気がつかない。 その日は喫茶店でお茶を飲み、一時間ほど吉祥寺をぶらついて別れた。 そのうち夕飯をたべさせるからと連絡があり、私はその部屋を訪ねた。それがやがて、毎週のようになっていったのには、私も驚いた。もしかしたら、私は愛されているかも知れない。 女とDとの関係がいまひとつ飲み込めないまま、私は単純に飯を食わせてくれる姉貴分だと思うことにし、女も同じように振舞った。私はこのとき既に女に恋していたが、忠実な弟の役割をきちんと演じていた。 「今日はすき焼きにするからね」 女が買い物に出たあとの部屋で手持ち無沙汰のまま、寝転がってぼんやりしていた私だったが、机のブックエンドに立てかけてある日記帳が目に入った。いけないとは思いつつ、好奇心のほうが勝ち、私はその日記帳を開いた。 意外だった。私は女が呼んでくれるからその部屋を訪ねていたつもりだったが、女の意識では全く違った。しつこい男、自分は嫌だが無理やり来るから仕方がない、Dに悪い。最初は意味が分からなかったが、やっと、自分は歓迎されていないのだということだけがはっきりした。あとは、何が書いてあったのか良く覚えていない。文字を追うことさえできなかったのだろう。もうここに来てはいけないのだ。馬鹿で惨めな私。 「待たせちゃった」と言いながら女が帰ってきた。私は女が料理するのを黙って見ていた。食べ終わって、「有難う、俺、帰る」と平静を装って立ち上がったつもりだが足が縺れた。「まだ早いじゃないの」と言いながら同時に立ち上がろうとした女がよろめいて、ふたりは重なって倒れた。女のミニスカートが捲くれ上がり、白い下着が露わになった。突然、ある衝動が湧き上がり、私は女の頬を殴りつけた。何故だったか分からない。自分の惨めさへの嫌悪だったか、嫌いなくせにいかにも親切そうに振舞っていた女への憎悪だったか、私には判別ができない。しかし殴りつけた瞬間、私は自分の行為に驚いた。私は女を殴る人間だった。私の一瞬の躊躇の隙を狙って、女が反撃した。 「ちょっと待って、お布団敷くから」 これは何だ。女はDが好きなのだろう。私は邪魔なだけの迷惑な存在ではないのか。意味が分からなかった。私はこんなことは期待もしていなかったのに。 その夜、布団の中にいるとドアを叩く音が聞こえる。電気は消してあるから黙っていれば不在だと思うだろう。しかし、ノックの音はしつこく、そのうちに鍵を開ける音が聞こえた。「やっぱり、来てたか」とAは鍵を見せながら平然として言うが、私は動転していた。Aはときどき大学で見かける顔だ。学部が違うから全学共通の大講義室での授業で見知ってはいたが話したことはない。  しかし、Aの存在はこれまで影もなかった。どこでAと女とが繋がっているのか。Aの要求で女は冷蔵庫からビールを出し、それから三人で飲んだ。会話が弾むはずがない。私は押し黙ったままだったし、Aもほとんど口を利かない。女はこの状況をどう凌ぐつもりなのか、わざとらしく明るく振舞っている。
しかし、Aの存在はこれまで影もなかった。どこでAと女とが繋がっているのか。Aの要求で女は冷蔵庫からビールを出し、それから三人で飲んだ。会話が弾むはずがない。私は押し黙ったままだったし、Aもほとんど口を利かない。女はこの状況をどう凌ぐつもりなのか、わざとらしく明るく振舞っている。Aが「やっぱり」と言う以上、私のことはAに知られていたということだ。私に分かったのは、Aも女と予備校で一緒だったという事実だけだった。Aはどういう気持ちだったのか。私はまだ二十歳にもならない子供だったが、今思えば、Aだってまだ一つしか違わないガキだ。落ち着いているようには見えたが、精一杯の強がりではなかったか。 その夜は女を真ん中に川の字になって寝たが、眠れる筈がなかった。一体どういうことになっているのか。なぜ、布団を敷くと言ったのか。女の好きなのはDではなかったのか。なぜAが鍵を持っているのか。Aは怒らないのか。私の貧弱な頭脳ではまるで整理がつかなかった。なぜ、こんなややこしいことに私を巻き込むのか。私の女への感情は憎悪と言って良いものになった。 この日を境に、何も知らない子供だった私の世界は変わった。私は屈託を抱え、なにもかもに嫌悪を感じる怠惰な男になっていった。この頃、三島由紀夫が市谷の自衛隊で自決し、世の中は騒然としていたが、私には関係がなかった。世界は私とは無関係に動いていた。 もう、あんな狂人たちの世界に近づいてはいけない。二度と会うまいと私は思った。 しかし、どういう積りなのか、女からはそれまで以上に頻繁に電話が来るようになった。どうして来ないのか。明日は必ず来て。三度に一度位はそれに応じて女の部屋に行った。行く度に後悔した。 「馬鹿ね、日記見たんでしょ。あれはね」と布団の中で女は囁く。Dに見せるものだった。本当の日記は鍵をかけて仕舞ってある。「だって、Dって酷い、殴るんだよ。あんたと何かあるんじゃないかって。信じられないよ。だから。」 Aは何なのだ。「鍵は知らなかったよ。多分、前に来たときに勝手に複製したんだと思う。だから新しく替えたの。」 理屈はどうでもつけられるが、要するにDともAとも、そういう関係になっているのだろう。「とにかくもう、二度とお前とは会わない、電話もするな」と言ったが、まるで効き目がない。私が行かなければ、向こうから私の部屋に押しかけてきた。私は父親の勤務する会社が関係する寮に住んでいるから、頻繁に女が来るようでは外聞が悪い。結局、根負けしてその部屋に行くようになる。私は、どこをどう探せば決着をつけられる出口があるのか分からないこの状況に、まるでなす術なく立ち往生しているだけだった。 「私、妊娠したよ」と告げられたのはいつのことだったか。呆然としている私に、「大丈夫、気にしないで」と女は言う。「でもちょっとお金がね」 女がそうであると言った以上、責任は私にあるのだ。 金は私が用意することになった。二、三日考えあぐねているうち、寮の近所に私も時々入ったことのある喫茶店があり、いつも入口にウェイター募集のチラシが貼ってあることを思い出した。 恥ずかしさを堪えて前借を頼む私に、私の住んでいる場所を聞き、それならば大丈夫だねと二ヶ月分の給料にあたる金額を、主人が出してくれた。 喫茶店では私は一所懸命働いた。夕方五時から閉店までが約束の勤務時間だったが、授業のない日は朝から出た。仕事は忙しかったが、整理のつかない混乱の中にいた私が、働いている間はその屈託を忘れることができた。 二ヶ月経って、前借分をちょうど済ませたと思えたとき、マスターが「良くやってくれたから、続けて頼むよ」と五万円の給料をくれた。二ヶ月間は只働きのはずが、一ヶ月で済んだのだ。義理が生まれ、その後も仕事は続けられることになった。 女はそれからも私に会うのを求めた。私は断れなかった。 一方で、私は新しい恋に出会っていた。女と別れられず新しい恋とを平行させることは倫理に悖ると私には思われたが、どうすることもできなかった。私は既に倫理観を喪失していた。女も世の中も、そしてなにより自分自身が、嫌悪に満ちていた。 AやDはその後どうなったのか。少なくとも私の目に触れるところからは姿を消した。彼らは賢かったのだと思う。こんなややこしい、訳の分からない関係を続けていては、生きていることの意味さえ分からなくなってしまう。馬鹿だったのは私だけだ。 私は、この人生に希望を失っていた。自分は生きている価値のない人間だと思い定めた。「青春」が迷いの別名であるとすれば、これが私の「青春」の始まりだった。 |