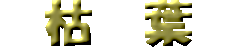
*** 匿名投稿 ***
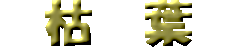
*** 匿名投稿 ***
2003年8月
|
「ねえ、ホントに蒼子さんって実在する訳ぇ?」 芝生に、自分で作ってきたというお弁当を三人分広げて、千枝子が聞いた。小春日和の穏やかな陽だまりでは学生が大勢、寝転んだり騒いだり、思い思いの格好をしている。 千枝子は私と同じゼミにいる。一週間ほど前、学食の前で私と宮野が「金ないし、パン買って分けるか」と呟いているのを聞きつけ、今度わたしが作ってきてあげると言っていたのが、やっと今日の弁当になったのだ。学部も違うのにしょっちゅう私の教室にやって来るので、千枝子も宮野を知っている。 「あっ、あれ、シローの妄想。でたらめ。全然、全く、架空の人物」 宮野はまた弁当を作ってもらおうと期待しているから、適当に嘘をつく。「そうでしょ、絶対、おかしいと思ってたよ。大体、自分からあんなに言い触らす人ってないよね。」言い触らした憶えはないが確かに皆の前で口にしたことはある。 弁当は美味しかった。「私はね、お料理得意なんだから。覚えておいて頂戴。」 越智がやって来て、「なんだよ、俺の分はねえだらか?」と文句を言う。静岡県三島の出身だから語尾に余計なものが混じる。「だって、越智くんはゼミ一緒じゃないもんね」「それを言えば、宮野なんか全然違うじゃん。」 「ねえ、越智くん。蒼子さんってホントはいないんでしょ?」「いや、昨日だって一緒に。な、シロー。」「え〜っ、宮野くん、どっちがホントなのよ」「千枝子さん、だから妄想だって言ってるべ。越智さんも夢みてるの。二人でからかってるんです。」宮野にとっては上級生なので、律儀に「さん」付けで呼ぶ。 「じゃ、行こうぜ」と越智が言うので立ち上がる。宮野も「俺も」と立ち上がった。「どこ行くのよ」「勉強、勉強」「宮野は関係ねえだんべ」「俺は来年のために」 「ちいちゃん、今日はサンキュウ。旨かった」と一応千枝子に礼を言って別れ、阿佐ヶ谷にある越智の部屋に向かった。この頃は宮野も阿佐ヶ谷に越していたから、どうせ同じだった。 昨日のことだ。 全く身につかなかったフランス語の授業もこれで終わりだ、しかし単位は取れるだろうかとぼんやりしていた私の耳に、来週の試験について伝達する、という教師の声が聞こえた。二年間、諸君とともにフランス語を勉強してきたが、どうも諸君の力は心許ない。一定の水準を測るために当然試験は行うが、最初から諦めている者のためにチャンスを与える。シャンソンの『枯葉』を覚えてきて答案用紙の裏に正確に書いた者には「可」を与える。そう言って、教師はざわつく教室を出て行った。 枯葉よ、絶え間なく散り行く枯葉よ。まさか日本語で良いのではあるまい。「きよみ」でランチを食べながらどうしようかと相談していると、蒼子が「私、レコード持ってるよ」と言った。何もなくて詩を、しかもフランス語を暗記することなど到底無理だが、歌ならば私の領分だ。「歌うんなら、ちょっと違うけど、カナも振ってあげる。」蒼子は仏文だからね。頼りになる。しかしプレイヤーはどこにある。「俺が持ってるだら」と越智も喜ぶ。それなら越智の部屋でレコードを聞きながら覚えることにしようと話が決まったのだった。 それが昨日のことで、早速今朝蒼子がレコードを持ってきてくれた。歌詞カードは拡大コピーした。 「大事だからね、慎重に扱ってくれよ」「大丈夫、任せなさい」 エディット・ピアフは悲しい。長い前歌はメロディーに乗せられずどうしても字余りになってしまう。苦労した。歌えなければ覚えられない。 「俺も勉強する」とついてきた筈の宮野は、とっくに飽きてしまって、部屋の隅に転がって『網走番外地』を歌っている。「ドスを、ドスを片手に殴りこみ、斬ったはったのこの稼業」「凍りつくよな星陰に、誰が書いたか片隅の壁に涙の侘び言葉」。 「やかましい。」 Oh! je voudrais tant que tu souviennes Des jours heureux ou nous etions amis En ce temps-la la vie etait plus belle Et le soleil plus brurant qu’aujourd’hui Les feuilles mortes se ramassent a la pelle Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du Nord les emporte Dans la nuit froide l’oubli Tu voirs, je n’ai pas oublie La chanson que me chantais C'est une chanson, qui nous ressemble Toi qui m'aimais, et je t'aimais Nous vivions, tous les deux ensemble Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais mais, la vie separe ceux qui s'aiment Tout doucement, sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants desunis 語尾変化がやや怪しいが、まあこれなら許してくれるのではないかと思える程度にはなった。あとは来週までに少しずつ固めていけば良い。既に外は暗くなっていた。私たちは『涼』で飲んだ。私は蒼子がどんなに素敵であるかを痴呆のように何度も繰り返し力説した。宮野は「一人でやってれ」と吐き捨て、越智は「いいじゃん、もっと喋らせろよ」と笑う。『涼』のお姉さんは「勝手にしな」と呆れていた。 試験の結果はめでたく「可」。これで充分だ。今日はお礼に蒼子を誘おうと宮野が言った。今回は彼には全く関係ないのだが。 私たちがいつも行くのは池袋西口のビルの中にある「パブ・エリート」だった。当時、パブという名の大衆マンモスバーが流行り始めていた。周りに三十人ほど座れる円形のカウンターの中にバーテンダーが二人張り付いていて、広いフロアにそんなカウンターが六つか七つある。私たちは迷わず木元さんのカウンターに座った。ここにはチーフと呼ばれる人と木元さんの二入が入っている。木元さんは鷹巣の出身で、私たちより五、六歳年上のちょっと苦みばしった顔のバーテンダーだ。たまにチーフの目を盗んで、私たちのグラスにウィスキーを注ぎ足してくれることもあった。宮野は不思議にこういう人を見つけてくる才能がある。 ジンのボトルを頼んで私はジンライム、宮野がロック、蒼子はジンフィズを飲んでいたが、そのうち木元さんが「ふたりのために」と言いながら、乾いた布巾で氷を包みアイスピックの柄で細かく砕いてカキ氷のようなものを作った。その上から、ジンをベースに二、三種類の酒をシェイクして注ぎ、溢れそうな氷の上部を少し固めた。最後にストローを半分に切って二本挿し、「どうぞ」と蒼子の前に置いた。白い氷の底に沈む色鮮やかなカクテル。 「どうするの」と首をかしげる蒼子に、「二人で一緒に飲むんだべ」と宮野が面白くなさそうに言い捨てる。蒼子は普段よりはしゃいでいるようだった。「それじゃ一緒に」と頬を近づける蒼子につられて私も顔を寄せたとき、「ゴメンゴメン」と木元さんが笑い声を上げた。 「やると思ったけどね。」こういうのは基礎知識だから覚えておいたほうが良いと教えてくれる。氷で固めてあるため空気の通りが悪い。ストロー一本では吸いにくいので、空気の通り道としてもう一本挿す。二本挿してあるのはそういう意味だ。決して二人一緒に飲むものではない。私と蒼子は赤面した。 木元さんはほかにも色々教えてくれた。シェイカーを片手で振るバーテンがいるが、あれは良くない。両手で正しく持って八の字に振るのが基本であり、なにごとも基本をないがしろにしてはいけない。プロフェッショナルは有難い。ほとんど実用の役には立たかったが、ひとつだけ後になって有益だと思えることがあった。「すごくお腹が空いているのに付き合いで飲まなくちゃいけない、会社に入るとそういうときがある。そんな時は、最初にウィスキーの牛乳割を一杯飲むんだよ。そうすると、牛乳が胃壁で膜になってくれるからウィスキーがすぐに吸収しないんだ。悪酔いしない。」 「蒼子さんの爪、なんだか少しおかしくねえか。」今日の宮野の言葉にはなんとなく険があるが、それには私も気がついていた。小指の爪だけが極端に小さく、少し変形しているようにも見える。「子どもの頃からね、爪噛むのが癖で、随分怒られてた。それからずっとこのまま。みっともないよね。恥ずかしい。」蒼子はひっそりと笑う。「そう言えば、シローもしょっちゅう爪噛んでるよな、欲求不満でねか?」確かに私の爪は、爪切りを使う暇もなくいつも深爪状態になっている。蒼子が笑う。「爪を噛むのはカルシウムが足りないんだって。」 そのうち、宮野がだいぶ酔ってきた。ずっとジンをロックで通してきたからだろう。 勘定を済ませると「今日は俺が蒼子さんを送って行く。おめは帰れ」と理不尽なことを言い出す。何を言っているか。しかし、宮野は強引に蒼子の腕を取って、先に歩いていく。蒼子の肩に宮野の腕が回る。 山手線で池袋から渋谷へ出て、東横線に乗り換えて武蔵小杉。電車に乗っている間中、宮野はこれ見よがしに蒼子の腕を抱える。バスで十分ほど行ったところに蒼子の住んでいる寮がある。その間も宮野の腕は蒼子の腕に絡まったままだった。蒼子もニヤニヤしている。二人で私に意地悪をしている。悔しい。宮野のアホ。次第に気持ちが険悪になってくる。 「それじゃ今日は有難う」私たちを等分に見つめながら囁いて蒼子が寮の玄関に消えていった途端、怒りが堰を切った。 「おめとは口きかね、絶交だ」「俺もだよ」と二人で顔を背け合い、やってきたバスに乗った。新宿から私は小田急線に、宮野は中央線に乗り換えたが、ひと言も交わさずに別れた。一人になった小田急線の中で、なんだ、宮野も蒼子が好きなのではないかと、鈍感な私はやっと気がついた。馬鹿な宮野。そしてもっと馬鹿な私。胸の底に、誰へとも分析できない嫌悪感が溜まっていた。その後一週間ほどの間、「お前らどうしたんだら」と越智が不思議がっていたが、私たちは一言も口をきかなかった。 ピアフの気だるい歌声が前触れもなくふいに頭の中を流れることがある。 エ・ル・ソレイユ・プリュ・ブルラン・クォジュルドゥイ。二本のストロー。小さな爪。グラスを見つめて頬を寄せてきた蒼子の薄っすらと染まった白い横顔。トワ・キ・メ・メ・モワ・キ・テ・メ。あれは遠い想い出。けれども。メ・ラ・ヴィ・セパール。 『枯葉』は少し切ない。 |