
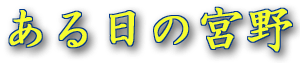

 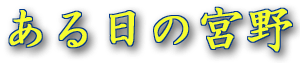 
|
2003年8月
|
原作中の実名は全て仮名に変更しました(HP担当)
「頼む、改札で待ってでけれ。三十分ぐらいで着くと思うがら。」 電話の声はなんだか随分遠く聞こえた。改札で待っていると宮野が肩を落としておぼつかない足取りで電車を降りてきた。今では地下鉄が乗り入れて随分大きな駅舎になってしまったが、当時の代々木上原駅は、線路をはさんで上下線の短いホームがあるだけの、急行の止まらない小さな駅だった。平日の昼時で乗客も少なくすぐにその姿が見えた。 「まず、切符の精算してけれ、出られねがら」 駅員を前に改札の向こう側で詰まらなそうに言う宮野の顔は少し細くなっていて、眼の下に隈が出ている。顔色が悪い。西武新宿線の沿線に住んでいるから、高田馬場・池袋間の国電の定期券は持っている。当時の新宿駅は国電から小田急線へは切符を買わずに通り抜けることができたのだ。出るときに精算すれば良い。国電という名称はその後死語になった。後にJRなどという面妖な社名に変ってE電という呼称を流行らせようとしたが、誰も使わずにいつの間にか消えた。 三日間何も口にしていないと宮野は私に訴えた。たまたま部屋の隅に転がっていた十円玉を見つけなければ電話もできなかったのだそうだ。とにかく飯が食いたい。 「お前がいねば死ぬどこだった」「何する?」「カツ丼」 駅前の蕎麦屋に入った。 「三日間、なにしてた?」「学校さは行ってあったどもな」「せば、誰かに借りれば良がったべせ」「他人から金借りる訳にはいがね」 学校の食堂なら五十円でラーメンくらいは食べられる。他人と言ってもクラスメートではないか。ちょっと昼飯代を借りる位はできるだろうと思うのは人間を知らない。折角のカツ丼を半分も食べずに「駄目だ」と言って箸を投げ出した。それでも少しは落ち着いた様子なので部屋に帰った。駅からははじめ急な登り坂になっているため、宮野の足は時々よろめいた。 「なにしろ、腹が減りすぎてヨ、全然眠られねんだな、参ったよ。大体、お前が学校さ来てれば何の苦労も無かったんだ」。 私の方は本来夕方からポーションに行けば良いのだが、昼間のアルバイトが急に辞めてしまったため、朝九時半から夜の十時までの仕事を三日も続け、やっと今日から二日の休みを貰ったところだった。 「仕送りはいつ来るんだ?」「来週の月曜日。それまで何としても生ぎねばねんだ」 まだ四日もある。私の手元には、特別手当だと、昨日マスターがくれた二万円がある。彼もアルバイトでもやれば良いのだが、絶対にしない。夏休みに帰郷した時に、父親の勤務している書店で少し手伝うだけが、高校時代から経験している唯一のアルバイトだ。東京では一切働かないことに決めている。しかし仕送りだけで暮らすのは容易ではない。まして宮野は酒を飲む。酒を止めなければ絶対死ぬ。 「俺は、必ず親父と一緒に独立して本屋やるんだよ。それ以外の仕事なんか、やるわけには行がねんだ」 分かるようで分からない理屈だが、本人が言う以上やむをえない。 「さて、今日は昭和二十年代に致しましょうか?」と眼をしょぼつかせながら宮野が言った。この頃、私たちは『昭和の歌謡曲』という本を買っていて、一頁目から思い出しながら歌うという、下らない遊びをしていた。不思議なことに最初は全く歯がたたないだろうと思っていたが、時には二人のどちらかが思い出し、そのため大袈裟に言えば未踏峰の山を少しずつ征服していくような感覚を私たちに持たせた。しかし、眠いのだろう。少し寝ていた方が良くは無いか。 「大丈夫、大丈夫。二十年代だば、結構分かると思うんだ。戦前の部分で苦戦したのとは違うべ。」 『リンゴの唄』(並木路子)、『かえり船』(田端義夫)と順調な出だしだった。『かえり船』は名曲です。『悲しき竹笛』(近江俊郎・奈良光枝)で躓いた。美空ひばりの『悲しき口笛』と混乱してしまう。どうしても分からないのが数曲続いた後、『東京の花売り娘』(岡晴夫)、『星の流れに』(菊池章子)でやっと息をついた。結構難しい。『麗人の唄』『青春のパラダイス』『雨のバラ』『お夏清十郎』、こんな唄を知っている奴がいるのだろうか。カラオケというものがまだ誕生していなかった時代、金の要らないささやかな遊びだった。 テレビもラジオもなく、ボーリングなど金と体力の無駄と私たちは思っていた。ボーリングをやる金があれば池袋のモッキリ屋なら二杯は飲めた。モッキリと言うのも姿を消した商売の一つだ。本当は酒屋の店頭で飲ませるのは違法なのだが、ちょっとしたテーブルを脇において柿の種でも出せば、それは酒屋ではなく、併設した居酒屋であるというのがその理屈だったらしい。コップに盛り切り一杯というのが語源だと思う。  「明日は学校さ来るんだか?」「サテンも休みだから行ぐよ」
「明日は学校さ来るんだか?」「サテンも休みだから行ぐよ」それなら、昼間『緋牡丹博徒』を見て夜は蒼子を誘って飲みに行くぞと宮野は勝手に決めた。折角渡した金も結局そういうことに遣ってしまうのだ。私と蒼子の受講科目を全て知っていて、どの教室で会えるかが彼の頭の中には完全に入っていた。だから蒼子には連絡しなくても大丈夫だろう。三日間、空腹を堪えながら無理をして学校に行っていたのも、必ず私に会えると信じていたからだった。 そろそろ夕方になってきた。「ちょこっとだけ」と近所の焼き鳥屋に行ったが、三日間の空腹を凌いできた宮野の胃は酒を受け付けず、二合を二人で空けられなかった。私もなんだか疲れていたが、トリスバーに席を替えてシングルを一杯ずつ飲んだ。ほとんど飲んでいない宮野だが、すでに口調が縺れ始めて同じことを何度も繰り返す。お竜さんは最高です、蒼子とは比べられません。余計なことだ。 「せば明日、教室さ行くよ」と宮野は帰って行った。 |