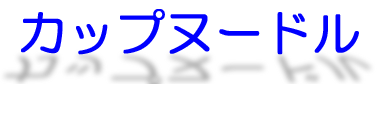
*** 匿名投稿 ***
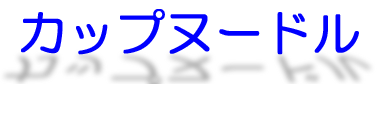
*** 匿名投稿 ***
2003年10月
|
原作中の実名は全て仮名に変更しました(HP担当)
「うわっ、酒臭い。酷いな、これは」田村が大声で喚きながらカーテンを開き、窓を開け放した。  眩しい。頭が痛い。吐き気がする。死にそうだ。「また宮野さんでしょう。いい加減に生活改めなくちゃ、死んじゃいますよ。」声が脳髄に響く。夕べは宮野と池袋の「天狗」で「新政」を飲み過ぎた。「ああ、ジーパンも酷いよ。洗濯してあげますからね。全部脱いでください。」
眩しい。頭が痛い。吐き気がする。死にそうだ。「また宮野さんでしょう。いい加減に生活改めなくちゃ、死んじゃいますよ。」声が脳髄に響く。夕べは宮野と池袋の「天狗」で「新政」を飲み過ぎた。「ああ、ジーパンも酷いよ。洗濯してあげますからね。全部脱いでください。」そう言われてみるとジーパンのまま寝ている。裾には反吐のような汚れがこびりついている。吐き気を堪えて裸になりまた布団に潜り込む。 「今日『影』は?」「いつもと同じ、五時から」「じゃ間に合うから、その学生ズボンも洗っちゃいましょう」 『影』ではワイシャツに黒いズボンという決まりになっているので、私は高校時代の制服のズボンを穿いているが、これもしばらく洗っていない。今脱いだものと、部屋の隅の紙袋に突っ込んである汚れ物とを一緒に抱えて、田村は出て行った。 私たちは「K会社上原子弟寮」に住んでいた。地方の支店に勤務していて、東京の大学に子どもを入学させた社員のために、子どもたちを安く収容してくれる施設だ。おそらく最初は独身寮の積もりで建てられたのだろうが、社員は誰も入居しなくなり、そのお蔭で子弟寮ということになったのだと思われる。四階建ての一階には食堂と風呂、それに舎監夫婦と管理人、賄いのおばさんたちの部屋がある。舎監は元京都大学の事務長をしていたという、いつもパイプを銜えている老人で、学生からは煙たがられている。入寮して数日後に部屋に呼ばれたことがあるが、互いに何も話すことがなく、全く無駄な時間を費やした。   二階から四階までが寮生の部屋になっていて、四十人ほどの学生が暮らしている。それぞれの部屋は四畳ほどの広さの洋室で、壁際に作り付けてあるベッドの下が抽斗になって、衣服が収納できる。ベッドの足元からは三十センチほどの空間を開けて、天井までの高さで、押入れ兼洋服ダンスにもなる物入れもしつらえてある。窓際には小さな机も設置されているから、狭いが割りに便利な造りだ。バス・トイレのない最低ランクのビジネスホテルを想像してみると良い。
二階から四階までが寮生の部屋になっていて、四十人ほどの学生が暮らしている。それぞれの部屋は四畳ほどの広さの洋室で、壁際に作り付けてあるベッドの下が抽斗になって、衣服が収納できる。ベッドの足元からは三十センチほどの空間を開けて、天井までの高さで、押入れ兼洋服ダンスにもなる物入れもしつらえてある。窓際には小さな机も設置されているから、狭いが割りに便利な造りだ。バス・トイレのない最低ランクのビジネスホテルを想像してみると良い。ただし、私の部屋は隣室と一枚のドアを共有している。ドアを開けると真ん中に仕切りの壁があり、右側が私の部屋、左にはそれと左右対称になった部屋がある。それぞれの部屋の中が丸見えにならないよう、カーテンで遮っている。各階の両端がこのタイプで、他は全くの個室だ。初めて寮に入ったときにこの部屋をあてがわれ、半年ほど経ったころ個室に空きがでたのだが、わざわざ移るのも面倒で、そのままここに住んでいる。幸い、去年一緒だった奥山も、今一緒にいる田村も私の神経に障る人間ではないのが助かった。 朝晩の二食がついて一万円の寮費は父親の給料から天引きされる。夕方五時には、一度に十人ほどが入れる風呂が沸く。十一時には火を止めるがそれから一時間くらいは充分熱い。各階の洗面所には洗濯機が二台置いてある。玄関の鍵は締められることが無いので、実質的に門限はない。予め連絡して食事を抜いた場合には、朝飯百円、夕飯二百円の計算で、月末に私たち自身に返金してくれる。その仕組みが分かってからは、当然私は朝飯を抜くことに決めたので、毎月三千円が戻ってくる。天国というものではあるまいか。只みたいなものだが、会社の福利厚生の一環だからだろう。親は助かった筈だ。 田村英一は私より一年後に隣室に入ってきた。元々は東京の育ちだが、大学入学と同時に父親が水戸に転勤になったのだ。昭和二十八年三月の生まれだから、私とはほとんど二つも違うのに、一ヶ月も経たないうちから、どういう訳か、自分がいなければこの男は生きていけないらしいと思い定めてしまったようだ。 私は、寮費とは別に昼飯代その他の小遣いとして、親から一万五千円の仕送りを受けていた。入寮の挨拶にやってきた田村の母親がそれを聞き、彼の仕送りも同額に決まった。あとで他の寮生の間を調べて回った田村が、「みんな大体三万円くらい貰ってますよ」と憮然とした表情で文句を言った。しかし、それは私のせいではない。 昼過ぎ、やっと頭痛と吐き気も少し治まり空腹を感じた頃、田村がラーメンを作ってくれた。部屋で火を使うのは禁止されているが、学生の夜は長くどうしても夜食が欲しいので、皆それぞれ工夫して何かを作っていた。田村は登山に使う携帯用の鍋でラーメンや豚汁を作る。時にはすき焼きも作ってくれる。 やっと私は布団から起きだした。服は洗われてしまったから丹前を着た。豪華。卵が入っている。「昨日買った卵ですよ。谷山の冷蔵庫に入れて貰ってた。」谷山の部屋には冷蔵庫があるのか。テレビを持って寮に入ってきたのは彼ひとりだから、多分、大金持ちなのだろう。しかし、父親が同じ会社に勤めているのに、なぜ、こんなに違うのか。 「あなた毎月五万も稼いでいるのに、なんでこんなに金ないんですか?不思議でしょうがないですよ。」私も不思議だ。「アルバイトしたら普通、服を買うとか、何かするでしょう。旅行するとか。あなた何もしないし、多少増えたのは本だけじゃないですか。たまにはズボンくらい買いなさいよ。それにいつだって腹減らしてるし。」 五万円を稼ぐ私が、アルバイトもしていない田村に飯を食わせて貰っている。不思議なのはお前の方だ。「だって、ボクは煙草も吸わないし、喫茶店行かないし、学食で食ってるだけだから、全然必要ないんですよね。」百五十円の定食が最高で、かけ蕎麦やカレーライスはもっと安い。少し本を買ってもまだ充分に余裕がある。「大体ね、朝晩ちゃんと食べてれば昼なんか抜いても良いんですよ。」 「貯金してますからね、月に七千円はできますよ」というから信じられない。「コーヒーと煙草と酒、これは無駄の極致というべきです。」それならば私の人生は無駄そのものだ。「そもそも、あなたが仕送り一万五千円だって言うから、ボクはそれに合わせた生活してるんじゃないですか。」  煙草を吸おうと机に手を伸ばしたがハイライトが見当たらない。昨日帰りがけに買ったばかりでまだ二、三本しか吸っていないはずだ。灰皿もない。「捨てちゃいました」と田村が平然と言う。さっき洗濯物を持っていくときに捨てた。なぜ、そんな意地悪をするのか。「買ってきて、お願い。」煙草は百害あって一利も無い、あなたの身体を考えているのだと口うるさい。「あなた、自分の歌に自信もってるんでしょ。時々声がかすれるのは煙草のせいですよ」。「分かったから煙草をくれ、何も言わずに煙草を下さい」。私の哀願にとうとう根負けして、実は隠しておいたと自分の部屋から持ってきた。
煙草を吸おうと机に手を伸ばしたがハイライトが見当たらない。昨日帰りがけに買ったばかりでまだ二、三本しか吸っていないはずだ。灰皿もない。「捨てちゃいました」と田村が平然と言う。さっき洗濯物を持っていくときに捨てた。なぜ、そんな意地悪をするのか。「買ってきて、お願い。」煙草は百害あって一利も無い、あなたの身体を考えているのだと口うるさい。「あなた、自分の歌に自信もってるんでしょ。時々声がかすれるのは煙草のせいですよ」。「分かったから煙草をくれ、何も言わずに煙草を下さい」。私の哀願にとうとう根負けして、実は隠しておいたと自分の部屋から持ってきた。非常に生真面目だが、考え方に独特な傾向がある。寮に入ってきたときには一冊の本も持っていなかったが、しばらく私の部屋の本棚を眺めているうち、「ボクも本読もう」と言い出した。 まだ本もないのに最初に本棚を買って来るのが奇態だ。しかも高さが百九十センチもある大きな木製の棚だ。部屋が一遍に狭くなる。(奥行きがあるから、二重につめると文庫本なら七百冊は収納できる。後に彼はこの本棚を持て余し、私の百二十センチの棚と交換した。) それから古本屋の店頭に均一本としておいてあるものを中心に、毎日二、三十冊ほど買って帰り、棚に並べ始めた。一週間で二百冊ほどが並んで漸く準備が整ったらしい。何を集めたのかと見てみれば、海外ミステリーの主な作家は大体網羅されている。「初めてミステリーの世界に入るわけだから、系統立てて押さえておかないと」と言う。人はこのようにしてミステリーを読むものだろうか。 ある種の完全主義者なのだが、完全主義は摩擦を起こしやすいし、ついに己が満足できる結果は実現されない。だから田村は常に偽痒のようなものを感じているらしく、何かといえば私に愚痴をこぼす。私の行く末を心配しているくせに、人間関係や処世について私の判断を求めるのも奇妙な話だ。生活能力はないが判断はできるらしいというのが、田村の、私への評価だった。 試験の前にきちんと勉強するのも、やはり真面目な性格を表している。一度、歴史理論のことで質問を受け、私は井上幸治教授の史学概論で覚えたマルク・ブロック『歴史のための弁明』を本棚から抜き出して薦めたが、役にたたなかったようだ。同じ史学科なのに、田村の通う国学院と私の大学では随分ようすが違う。国学院では、史学概論は神皇正統記や新井白石から始まるらしい。私の受けている講義は、歴史認識についてのマイヤーとウェーバーの論争から話が始まっていたから全く参考にならない。フランス語?私に聞くな。それからは学問について私に質問するのは諦めた。 「一度くらい蒼子さん連れて来たら良いじゃないですか。ボク頼んであげますよ。この人お願いしますって。」あなたを見ていると心配で仕方がないと、田村は聞き飽きた台詞を繰り返す。寮にいるときは丹前姿で寝ているばかりだし、出かけたと思えば大概は酔っ払って帰ってくる。本は読んでいるが勉強しているのは一度も見たことが無い。着ているのはいつも同じもの。あんなにアルバイトをしているのに、いつだって金がなくて腹を空かせている。この人はちゃんと生きていけるのだろうか。本当にボクは心配です。 年下の男に、私は何故こうも訓戒されなければならないのだろうか。 「あなたはテレビ見ないから知らないでしょう。カップヌードルっていうのが出たんです。」テレビは食堂に置いてあるが、ほとんど見ないし、新聞も読まない。だからコマーシャルも知らないが、そういうものが売り出されたと誰かに聞いてはいた。要するに昔の即席ラーメンと同じではないか。お湯を注ぐだけで旨いものになるとは思えない。それにひとつ百円もするという。インスタントラーメンが三個、特売なら四個は買える。そんな高いものを誰が買うのか、売れるはずがないと私は見当をつけていた。 「谷山が食ってました。」大金持ちだからね。「それでね、寮費を値上げしても良いから、もっと旨い飯を食わせるように団体交渉しようって。とんでもないヤツですよ、全く。」 飯が食えるだけで有難いではないか。ご飯は丼に大盛りだし、遅くなる時は連絡さえすれば名札をつけて別に取り除けておいてくれる。電子レンジがあるから冷えたもので我慢する必要がない。 夜中になって、名札のないものが二、三人分は残っていることがあり、運が良ければそれを頂戴することができる。おかずがなくて飯だけが残っていたときは、マヨネーズをかけて食べたこともある。私は充分に満足していた。そういえば、谷山はしょっちゅう不味いと文句を垂れていたのを思い出したが、家ではよほど旨いものを食べていたのか。しかし値上げは冗談ではない。馬鹿ではないか。 カップヌードルを食うような人間はろくな者ではない。カップヌードル自体もろくでもない。すぐに売れなくなるだろうと思った私の予想は、その後の歴史で裏切られることになるが、幸い値上げに賛成するものはひとりもいなかったので、谷山の提案は消えた。 久しぶりにからりと晴れた上天気で、出かける前には洗濯物も全て乾いた。私の学生ズボンには田村がアイロンまで掛けてくれた。「今晩、豚汁つくっておきますよ。」少し口うるさいのが難点だが、この男を妻にすると便利かも知れないと私は思った。 注)カップヌードルは、一九七一年に日清食品が売り出したのだが、年表によれば「チキンラーメンを紙コップに入れて食べている人を社長が見て、開発に乗り出した」。一九九五年までに百億食を突破したという。 |