![]()
![]()
![]()
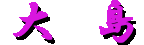
*** 匿名投稿 ***
2003年8月
|
小学館が空前の規模の国語辞典をつくるのだということが、大きな話題になっていた。英語のOED、漢和の「諸橋」に匹敵する、日本語辞書の決定版だというのが謳い文句だった。語彙や用例を集めるスタッフも半端な数ではなく、大量に人を募集しているというのは女の口から聞いていた。そこに採用されたと嬉しそうな声で報告する。採用と言っても、使い走りのアルバイトに過ぎないのだが、清少納言が好きで、もの尽くしなど暗誦できるほどだ。言葉への愛着は人一倍強い女だから、喜ぶのも当然かもしれない。 「だからね」と女が言った。仕事が始まるのは来週だから、お祝いに旅行をする。行き先は大島。既に船の切符は買ったしホテルは予約した。「だから、来て頂戴」と言って電話は切れた。 何故だ。これまでにもう何度も、二度と会わないと通告してきた。その都度、分かったと言いながらまた電話をしてくる。今度は旅行だ。何を考えているのか、女の気持ちが私には理解できなかった。 行くべきではないのは分かっていた。夏休みで帰郷している蒼子の帰りを私は待っている。なにを好んで女と旅行することなどあるか。だが、私がもし行かなければと、奇怪な連想が浮かんでくる。大島、三原山、投身自殺。何も決断できず、ただ事態が進むに任せていく私の、決着を先延ばしにする自己弁護の心理学だったに違いない。宮野は、絶対に駄目だと怒った。 まだ二人の間が、ひとつの事件をきっかけに決定的に変質してしまう前、飯を作ってくれるやさしい姉とそれに甘える弟という役割を巧妙に演じていた頃、いつも腹を空かしている宮野をその部屋に連れて行ったことがある。ろくに挨拶もせず、食事を終わるとすぐに、帰るぞと宮野は立ち上がった。あとで女は「あのひと、大嫌い。もう絶対つれてこないで」と私を責めた。宮野は妙に感の鋭いところがある。二人の間に漂う何か危ういもの、いっそ淫靡な雰囲気に、私自身は気付いていなかったが、潔癖な彼は気が付いていたのだ。 これっきり、これが最後と言い訳しながら、指定された日、私は竹下桟橋にいた。 今日のために新調したに違いない。真新しい水玉模様のワンピースにバスケットをぶら下げ、大きなつばの帽子を被っている。私のほうは、一年中ほとんどこれだけで通しているジーパンに下駄履きだった。 夜の竹下桟橋で乗船を待っているのは、ほとんど若い男女連れだった。「みんな、わたしたちみたい」。下らないことを言うな。彼らは少なくとも二人の意思が一致してここにいる筈だ。私たちとは全く違う。 夜の太平洋は真っ暗だった。「星が降る」という表現が誇張ではないと、そのとき初めて知った。甲板には寄り添う二人連れが幾組も、やはり感激した様子で黙って星を見ている。女が私の腕に絡まっている。星の下で、私はちっぽけだった。女も同じことを考えていたのだろう。「わたしたちって、小っちゃいね」と呟いている。 黒い波がうねりを上げる。空には満天の星。私の心には自分への嫌悪感と後悔。来るべきではなかった。 『アンコ椿は恋の花』が煩く流れる中で上陸した波浮の港は、白秋の歌碑があるだけで他には何もなかった。 風景などというものに全く関心がなかった私には、大島の描写はできない。ただ、青い空、青い海。三原山では下駄の歯に溶岩が挟まって歩きにくかったが、構わず登った。先を一人で歩く私に「イジワルね。ちょっと待ってよ」と女は小走りに追いついて、腕を絡めてくる。 「あっ、あそこ、牛。」珍しくもないだろう。詰まらないことにもすぐ反応して女は喜んでいた。 ホテルに着いた頃にはさすがに疲れていた。 夕食は大きな宴会場で、私たちが入って行った時には既に何組もの宿泊客が食事を始めていた。酒はどうするかと聞きに来た仲居にビールと酒を注文しながら、「私たち、新婚旅行なの」と下らない嘘をつく。誰が信じるものか。私のほうは肩まで伸ばした髪に、髭も半月ほど剃っていない。せいぜい、女を騙して遊んでいる不良学生にしか見えないだろう。しかし私はもっと悪い。 ここまで私は一銭も使っていなかった。途中のバス代も昼食も全て女が支払った。ホテルにチェックインしたときの前金も女の財布から出た。今吸っているハイライトもさっき売店で女が買った。「買うとき恥ずかしかった」と言いながら出してくれた着替え用のパンツを、今私は穿いている。私は女の金で遊んでいる恥知らずなヒモだ。 驚いたことに、今日一日、私はそれなりに楽しんでいたのだ。久しぶりに東京から逃れ、南国の真っ青な空を見上げているとき、心が平安を取り戻していくようだった。しかし女の顔を見ればまた気持ちが違ってくる。私は卑劣な人間だった。 布団に腹ばいになったまま煙草を吸っている私に、隣の布団から「どうしたの。こっち来てよ」と囁いてくる。吸い終わってもまだ黙ったまま身動きもしないでいると、いきなりこちらの布団に入ってきた。 「あんた、蒼子さんのこと考えてる」声が泣いている。「あんただけ、しあわせなんて、絶対嫌。あたし、嫌だからね」と体を押し付け足を絡める。蒼子のことは口にするな。平手で顔を殴ったが、ますますしがみついてくるばかりだ。私は抵抗を諦めた。 蒼子の白い横顔が脳裏に浮かぶ。私はここで何をしているのだろう。女が口にした「しあわせ」という言葉が心に堪えた。私にしあわせなんか来る筈がなかった。 翌日も悔しいほどの快晴で、半日島内を観光した後、帰りの船は夕方熱海へ着いた。 なんだかお腹が痛いのでもう一泊したいと女が言った。もうどうでも良かった。しかしこれも予定されていたことだった。旅館は予約されていて、すぐに離れの静かな部屋に通された。宿帳に、女は一所懸命嘘を書いている。「々妻」などと書いても誰も信じない。 部屋の窓を開けると専用の露天風呂が附属していて、私たちは一緒に入った。脇腹にある盲腸の手術跡が生々しかった。 大島のホテルとは違って、食事も部屋に運んで来た。料理を並べ終わって女中が「じゃ、奥さんあとお願いします」と部屋を出て行ったとき、浴衣に着替えた女は嬉しそうな顔をした。 「なーに、これって、まるっきり演歌じゃん」 「演歌だば俺さ任せれ。妻と書かれた宿帳に滲む涙の筆の跡。あっ、箱崎紳一郎『熱海の夜』だべ。大下八郎かも知れね」 「感覚が古いんだよね。歌うの聞いてればすぐに分かってしまう。アヴェ・マリアくらい歌って欲しいよ、全く」 そうだったか、私は気付かないうちに演歌を書いてしまっていた。「私」と「女」は演歌の登場人物だったのか。しかし、あのことを挟む数年間の「私」と「女」の交渉は、あれはただ演歌だったと済ませてよいか。多少は分析というものも必要ではないか。 「分析なんて関係無ぇ。おめは、ただのスケベだったのだ。女なら誰でも良かったから、のこのこと大島あたりまでついて行ったの。そのあともズルズルと」 「ホント、淫らなんだよ、お前は。ああ、いやらしい」 きちんと反論はできないが、それではあんまり「私」が可哀想ではないか。もう少し心理学的に、あるいは文学的に説明することはできないのか。しかし私は心理学者でも文学者でもないからな。 ナントセバイイベ。 「絶対良くないと思う。もし主人公の気持ちが、あそこに書いてあるとおりなら、倫理的に許せないよ。だって、蒼子さんがちゃんといるわけでしょ。フリンよ。あんたの好きな正義とは全然ちがうじゃない」 「あたしぁ全然、好きになれないね、ああいう男」 私は正義に憧れていた。怪傑ハリマオになりたかった。正義と倫理を持ち出さればいうべき言葉がない。不倫とは恐れ入るが、確かに倫理に悖る所業であった。 「これってさー、アダルトチルドレンってことでしょ?」 この用語が発明されて以来、何でもこれを使えば解決しそうに思えてしまうのが不思議だが、そうなのか。アダルトチルドレンにはいくつかの条件があり、幼少時からの家庭内での、性的なものをも含む虐待や暴行が重要な要件として挙げられる。その結果「共依存症」になった女は、駄目でどうしようもない男に尽くすようになる。(えーっと、これは私が自分で勉強したことではなく、斎藤美奈子先生の『読者は踊る』で教えられたことなのです) ホントかしらん。確かに「私」は駄目な人間だったが。しかし、「女」の育った家庭は、やや専制的な父親が君臨していたにしても、おおむね平和だったと聞いているから、この見解は採用し難い。まして「私」自身の育った家も、そんなことは全くない筈だからね。 「お前、女に惚れてたんじゃないの?ホントは」 これは絶対違うと断言してしまう。ある事件によって燃え上がった憎悪はやや変質して、「私」の「女」への気持ちは既に慢性的な嫌悪とでもいうべきものになっていたが、これを「惚れている」などと言われたら、たまらない。 「遺伝子のせいだと思う。あたしたちの行動は全てそれが決定するの。あんたがどう逆立ちしても無駄だったのさ。なにしろ遺伝子には逆らえないからね」 却下。ドーキンス『利己的な遺伝子』だってそんな無体な理屈は言っていない。 「お芝居してたっていうのはどう?彼らは一所懸命、不幸で、駄目な男女を演じていた。演じるうちにだんだんそれが快感に変わっていった。ほら、自己陶酔してる感じがすごく匂うよね、嫌なヤツ」 これはなんとなく文学っぽくて気になる意見だな。じっくり考えてみる必要がある。 こうして様々な意見を総合し、慎重な検討をした結果、私は以下の結論に達した。 「私」は太宰治の世界にどっぷりと浸かっていた、と仮定してみる。世界文学の中でも鬼子というべきこの閉じられた世界では、主人公は常にいい加減な駄目な男で、世間に容れられない不満を抱いている(という風にここでは要約してしまおう)。「私」はそこから、世間なんてこんなものだと勝手に侮り、ところが実際はそんな甘いものではない現実を前に、なす術を知らない状態に陥っていた。積極果敢に道を切り開く努力ではなく、なす術を知らない臆病な自分を正当化するために、自分は「駄目な人間だから」という弁解を用意するようになっていた。要するに私小説の主人公を気取っていたのだね。 それに加えて、嫌悪する「女」という格好の障害があった。この障害によって「私」の人生はまるで上手くいかない運命に決まった。悪いのは女だ。私は、駄目な人間であり、その上宿命的な障害を抱えてしまった。上手く行く筈がない。努力は無駄だ。 意思と行動力と知性が問題であるはずなのに、「私」は一切それらを放棄した。 これが「私」の内心にある根本的な問題だったのではないだろうか。「女」と完全に縁を切ってしまっては、折角見つけた重要な理屈のひとつがなくなってしまう。嫌いながら断固として縁を切れなかったのは、そういうことではないか。そして自虐は、いつもそれを暖めていると、いつか隠微な快感に変わっていく。 おそらく青年期に特有な一種の病だと思うのだが、「私」の場合には少し度が過ぎ、回復までの時間が長過ぎた。 うーん、この論理の展開。なんとなく説得力があるような気がしないだろうか。 「女」についてはついに謎だ。何故あのように「私」に執着していたのか。「私」の心が百万光年も離れてしまっているのはとうに分かっている筈だ。「私」は三十年後ならば「キムタク」にも比すべき美男だから、ペットとして連れ歩くのにちょうど良かったのかと考えてみるが、これは余り現実的ではないね。謎のままで仕方がない。女は分析すべきではない。 それからの「私」の課題は、自虐の快感からいつ脱出するのかということに絞られていくのだが、たぶん、それは経験というものの積み重ねでしか解決しなかった。なにひとつ知らずに勝手に世間を侮った罪は、その世間に笑われながら、しかしきちんとそれを知ることによってしか解消されない。しかし、何かのきっかけが必要だった。 その後、「私」が経験しなければならなかった様々な愚行は、病から回復するためのリハビリテーションだった。回復したとはっきり自分で納得するまでには随分時間がかかったが、「私」はそれに踏み切るきっかけを見つけた。見つけられた方は良い迷惑だったかも知れない。 そしていつか「私」も回復する。そこに至る過程は、愚かしく滑稽ではあっても「私」にとって大切ないくつかの物語によって構成されるだろう。そこに登場する人物たちは私とともに戦ってくれた戦友だと、未来の「私」は考えるだろう。 |