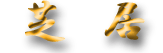
*** 匿名投稿 ***
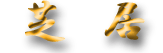
*** 匿名投稿 ***
2003年8月

原作中の実名は全て仮名に変更しました(HP担当)
"涼"は阿佐ヶ谷駅の南口からちょっと入った、一番街というこじんまりした商店街のほぼ外れに位置していた。 そこから二、三軒で一番街が終わり、右に折れてすぐに左に入ると私の部屋はあった。その頃、同級生の篠崎が郷里の三島に帰るため、敷金はそのままにしておくというのを幸い、手数料も半額にしてもらって、その六畳のアパートに移っていたのだ。市場の部屋も十五分ほどの距離にあり、篠崎が住んでいた頃から、"涼"は私たちの溜まり場だった。 その日、"涼"ではお姉さんが一人で所在なげにしていた。 「マスターは?」と問う私たちに、「あいつ。出て。行っちゃった。」「女。連れて」とボキボキと言い捨てる。おかっぱの前髪をまっすぐ切り揃えて、いつもと変わらない白いブラウスに黒のロングスカートだが、その顔はなんだかパサパサに乾いているように見えた。 「何だか気が滅入るからね、ぱっと行こう」と言いながら、私たちにはキープしているホワイトを出し、自分は日本酒にライムジュースを垂らした。「それって、マスターの飲み方だったべ」と市場が無神経なことを言う。確かにマスターが良く飲んでいたので私たちも覚えた。口当たりが良いのでつい飲みすぎてしまい、私はこれを飲むと必ず悪酔いした。 「でも、あいつも馬鹿。柚木さん、ごねんねって、権利証は置いてったからね。」 私たちはお姉さんと呼んでいたが、マスターはいつもきちんと「柚木さん」と呼んでいた。売れない役者だという色白の優男で、なんだか少し頼りな気だったが、酒は強かった。柚木さんもマスターと呼んでいたので、私は二人がそんな関係だったことを初めて知って驚いていた。 飲むうちに市場が「業っていう奴かな」と呟いた途端、お姉さんの姿勢が変った。「ナマ言うんじゃないよ、ガキの癖に。あんたなんかにゃね、一生分かんないことなんだ」何かが棘に触ったのだ。「怖い怖い」と言いながら、市場はすぐに退散してしまい、私だけが店に残った。 お姉さんがカウンターから出て、ジュークボックスで曲を選んでから私の隣に腰掛けた。 〜 逢えなくなって 初めて知った 海より深い 恋心 (『再会』) 「いいよわねぇ、松尾和子は。」こんなにあなたを愛してるなんて。私も小さな声で歌った。ああ、カモメにも分かりはしない。 「あんた、おとなになりな。男はガキじゃしょうがないよ。」私に説教しながら、酒のライム割を飲んでいる。酒が入ると伝法な江戸弁になる。年齢はいつまで経っても分からなかったが、多分私たちより十歳ちょっと離れていたのではないだろうか。私はなんだか辛くなって、別の客が入ってきたのを潮に店を出た。 翌日、うだるような暑さの中、昼過ぎの太陽が通りを隔てた向かいの屋根をぎらつかせるのを六畳の部屋でうつらうつら見ていると、外から声が聞こえた。「ハヤトくん、ハヤト!いるんでしょ」。窓の下を見下ろすと、お姉さんが「お芝居に行くよ」と手を振る。「芝居?」私はそういう世界に関係したことは一度もない。七面倒臭いのは嫌だ。「大丈夫よ。面白いんだから。」「お店は?」「休んじゃうから良いの。早くおいで。」 池袋から赤羽線に乗り換え十条で降りた。東十条につながる商店街のほぼ中間辺りにあるのが目当ての劇場だった。時代劇で見たような芝居小屋の造りで幟がはためいている。入り口で座布団を貰って煎餅を一袋買って座った。三十畳ほどあるのだろうか、畳の上にまばらに座っているのはオバさんやおばあさんばかりだ。ちょうど始まったばかりのようで、舞台の上では座長らしき役者が口上を述べていた。 芝居ははっきり言って退屈だった。忠臣蔵の何かのパロディらしいが、ギャグも古めかしく、素人っぽい感じがした。お姉さんはこんな芝居が好きなのかと横顔を窺うと、キャッキャと笑っている。パロディもギャグもまだそれ程一般的な言葉ではなかったが、私は中原弓彦を読んでいたから、芝居の実物は見たことがなかったくせに、何だ、この程度かと、生意気な感想をもった。ちょっと可愛い娘役だけが気になった。 幕が変わって、日本舞踊が始まった。ちょっと蓮っ葉な感じの、だが若くて可愛らしい娘が踊っている。さっき腰元の役で出てきて気になっていた娘役だ。「見てごらん、口をちょっと半開きにしてるだろ。あれが大衆演劇の踊りさ。本式のやつは絶対口を開けちゃいけないの。でも色っぽいでしょ。」とお姉さんが解説する。お姉さんは昔人形劇をやっていたから、こういう世界に詳しいのかも知れない。 人形劇の時代には『チロリン村とクルミの木』が初仕事で『ひょっこりひょうたん島』もやっていたというから私は尊敬した。今踊っているこの娘は半開きにした下唇がちょっと上を向いて、不思議な魅力があった。その流し目におばさんたちから盛んに声援が飛ぶ。一座の花形のようだ。 次のショーに移ってまた驚いた。掛け声がかかるまで分からなかったが、ウェスタン調の衣装を身に着け、野太い声で演歌を歌う色の黒い男が、あの娘なのだった。客席からはさかんに御ひねりが飛ぶ。 「あいつ、三宅にそっくりだね」とお姉さんが囁く。三宅というのは篠崎の高校時代の同級生で、山男だ。年中ぎらぎらした脂ぎった顔をしているが、山に登るためには普段から脂肪を蓄えておくのだと気にもしない。 終わって外へ出ると、出口には役者一同が勢ぞろいして挨拶する。あの男は眼鏡をかけていたが、そうすると、ほんとに三宅そっくりだと私も思った。 その後は新宿の「五十鈴」に連れて行ってくれた。うなぎの寝床のような狭くて奥の深い店に、背中を通り抜ける隙間もないほどカウンターに客が一杯詰まっている。やっと二人分の席を空けてもらい座った。カウンターの中には、中年というより老年と言って良い女性が数人、燗や料理の手配をしている。新宿では名高い店だとお姉さんに教えられて見回すと、私のような若造はひとりもいない。なんだか緊張してきた。 五十鈴を出て阿佐ヶ谷に戻ると、店の前で「ちょっと待ってて」とお姉さんが鍵を取り出す。手伝ってよ、と言いながら五センチほどの厚さの氷の板を半分に割ってボールに入れ、封を切っていないホワイトと一緒に私に持たせた。「あんたんとこで飲も」つまみはイカの燻製しかないけど良いでしょと、歩きだした。 窓を閉め切っていたため、部屋の中は熱気が篭っている。窓を開け、入り口のドアも開け放すと少し息がつけた。「あんた、扇風機くらい買いなさいよね」とお姉さんは怒るが、ここで飲もうと言ったのはあなたです。  しばらくする内、汗で気持ちわるいよ、何か着替えるものはないかとお姉さんが聞いてきた。私のTシャツではお姉さんの巨大な乳房が納まるとは思えない。壁に掛けていた浴衣を見て、これを借りるよと肩に羽織って、後ろを向いて服を脱ぎだした。昨日洗っておいてよかった。「これが暑苦しいんだ」とブラジャーも外してしまう。「涙の谷間」に汗が光る。帯は暑苦しいからいらないと、前を合わせたままで座ってまた飲みだしたが、イカクンに手を伸ばすたびに白い大きなおっぱいが乳首までこぼれてしまう。自分で気が付くと「ごめんごめん」と前を合わせるがすぐにまた開いてしまう。それに胡坐をかいているから、猫だか犬だか分からない動物が一杯踊っているパンツも丸見えだ。
しばらくする内、汗で気持ちわるいよ、何か着替えるものはないかとお姉さんが聞いてきた。私のTシャツではお姉さんの巨大な乳房が納まるとは思えない。壁に掛けていた浴衣を見て、これを借りるよと肩に羽織って、後ろを向いて服を脱ぎだした。昨日洗っておいてよかった。「これが暑苦しいんだ」とブラジャーも外してしまう。「涙の谷間」に汗が光る。帯は暑苦しいからいらないと、前を合わせたままで座ってまた飲みだしたが、イカクンに手を伸ばすたびに白い大きなおっぱいが乳首までこぼれてしまう。自分で気が付くと「ごめんごめん」と前を合わせるがすぐにまた開いてしまう。それに胡坐をかいているから、猫だか犬だか分からない動物が一杯踊っているパンツも丸見えだ。「あちしはね。」酔ってくると「あたし」が「あちし」になる。「惚れてたんだ。」「芝居はちっとも上手くなかったけどさ。」「お店、あちしに残していったんだ、いいとこあるじゃないか、え?」「あんた、女を泣かせちゃ駄目だよ」。 いきなり「ねえ」と低声になり身体を寄せてきた。「しようか」。ドキッとした。お姉さんごめんなさい、俺にはあなたを慰める力なんてとてもないよ、ガキだから。「だって」と口籠る私に、「バカ、冗談よ」と笑って、眠くなってきたと言いながら座布団を引き寄せ、二つに折って頭の下に敷いたかと思うと、すぐにクウクウと寝息を立て始めた。横向きに体を丸めて寝息を立てているお姉さんは、泣き草臥れてしまった女の子のようだった。可哀相なお姉さん。白い浴衣地から犬の顔が透けて見えるのを呆然と見ながら、俺、大人になるよと頭のなかで繰り返しているうちに、私もいつの間にか眠ってしまった。 後に『夢芝居』が流行ってきた頃、あの娘姿で踊っていた役者の名前を私はやっと思い出した。 後に柚木さんは"涼"を閉めたが、少し経って私たちと同い年のたけちゃんという板前と一緒に、「網代木」という小料理屋を出すことになる。「あさぼらけ宇治の川霧たへだへにあらはれわたる瀬々の網代木」からとったのだ。 |