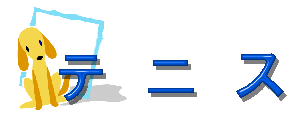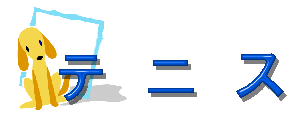「私たちみんな参加するから、絶対お願いね」
課長の指示で、終業後三十分ほどの時間、文子が私に英文タイプの特訓をしてくれている。それが終わって帰ろうかという頃、そんなことを言い出した。文子は短大の英文科を出ているからタイプができる。私は会社に入るまで触ったこともない。年度末の忙しいときには課長が先頭にたって、見積書の明細をタイピングしなければ追いつかないほどだった。私もポツリポツリとやっては見たが、足手まといになるだけで一つも役に立たなかった。業を煮やした課長が、今年文子が入社したのをきっかけに、一ヶ月で取り敢えず打てるようになれと、私に厳命を下していた。
いくら文子に怒られても、最初に我流で触ってしまった指は、正式な動きをしない。一つの単語を打つ度に、手はホームポジションから離れてしまうから、スピードが上がらない。もう指はどうでも良いから、早さだけを目標にしろという文子の言葉で、指遣いは無茶苦茶だが、なんとかある程度のスピードは確保できるようになってきた。その代わり、当然のことだがブラインドタッチは諦めた。思えば私の人生には、本式でない我流の欠陥がいつも付きまとっているようだ。
文子の話はテニス部に参加しろということだった。たまたま私たちの課の係長がテニス部長をしているのだが、若手の参加がなく最近停滞気味だ。これまでは軟式のクラブだったが、いっそ硬式に変更して若手を勧誘しようと、文子に声をかけた。彼女は自分の同期の女性を誘ったが、やはり男性も必要だと係長に言われたのだ。
私はスポーツが得意ではない。特に球技は駄目だ。遊びでやったソフトボールでも三振するし、ボールとは絶対に相性が悪い。他の連中の顔を思い浮かべても、まず、テニス部に入ろうなどという者はひとりもいないのではないか。
「だから頼んでるのよ。大体みんな、お酒ばっかりじゃなくって、たまには外で遊ばなくちゃ、体に悪いよ。宮野さんも誘ってみたら。」
確かに文子は健康そうだ。日焼けした(のだろうな)褐色の肌。すっきりと伸びた脚。美人ではないが愛嬌がある。飲むときにも気軽に付き合ってくれるから、若手の間では人気がある。それに引き換え、私たちの顔色の悪さはどうだろう。仕方がない、取り敢えず声だけはかけてみることにした。
宮野には声を掛けるまでもない。絶対にやらない。遅れてきた全共闘の小笠原は酒が弱く登山の趣味があるから、もしかしたらやるかもしれないと思ったが、休日は山があるから駄目だと断わられた。赤間は既に膨らみ始めた腹を持て余しながら、何かきっかけさえ見つければ猥談に転じようと待ち構えている男だ。声を掛けた私が悪い。「汗と精液は無駄に出さないようにしている」と嫌らしい笑いを浮かべる。
意外なことに矢澤と亀山が是非参加したいと言い出した。矢澤は、空手の有段者だがテニスや女には絶対縁がないだろうと思われた。私たちより一期上の入社なのだが、亀山のほうが年上なので、なんとなく同期と同じような感じで私たちは付き合っている。酒の飲み過ぎでいつも胃のあたりを押さえている。
「俺、絶対参加する」と矢澤は喜んでいる。「だってよ、お前、ミニスカートだぜ。いいチャンスじゃねえか。春美も来るんだろう?」浅草の男は言葉も荒いが、趣旨が違うのではないか。半年ほど前に酔って新宿のやくざと乱闘になり、片目失明の寸前までいったこの男も、今ではすっかり回復している。しかし、目つきの悪さは生まれ付いてのものだろうか。春美は「矢澤さんって怖い」と言っていた。私もこの男とふたりだけで飲むのは避けるようにしている。
亀山は酒乱だ。学生時代に肝臓を傷めたせいか、どす黒い顔をしている。課が違うから現場を見たわけではないが、酒席でうるさく説教をする上司を投げ飛ばしたと噂されている。テニスが目的ではないのは亀山もどうやら同じだが、口調だけは偉そうだ。「俺ほんとはテニス好きなの。機会がなかっただけ。卓球やってたから簡単です。教えてやるよ」ほんとかね。小学生のピンポンと硬式テニスとは余りにも違うと思ったが、これで何とか文子に顔が立つ。
ところが若い女性の方は結局文子だけになった。優子や春美は日焼けしたくないとか、練習場が遠いからとか訳の分からない理由をつけて断った。「ほんと、訳わかんないよ」と文子がぼやく。もしかしたら私たち三人が入ると知って怖気づいたのかもしれない。私たちは不良だと思われていた。
暑い日盛りの中、大宮運動公園のテニスコートに集合した。私、矢澤、亀山の三人はジーパンに裸足という格好だから、十五、六人いる先輩の部員たちの視線が冷たいが、仕方がないではないか。ラケットは二千円で近所のスーパーで売っていた。シューズはとうぶん我慢し、裸足で良いことにしたのだが、これがそんなに異様な姿に見えるとは予想もしていなかった。下駄で来たのが悪かったのか。どうも場違いなところに来てしまったらしいと私は思い始めていた。先輩の部員というのはつまり先輩社員のことだから、一番若くても私たちよりずいぶん年上で、余り気軽に話ができない。私たち新たに参加した四人だけがいつもくっついていた。
初めてやるテニスがこんなに難しいものだとは知らなかった。私たちのラケットはボールに敬遠された。それほど速い球ではないのに、何故空振りしなければならないのだろう。辛うじて当たっても、ボールの行方は一向に分からない。とにかく走り回っているだけで疲れた。先輩たちもそれほど上手いわけではなかった。軟式から硬式への切り替わり時だから腕の動きにやや奇妙なところがある。係長とその他二、三人だけはさすがに上手で、ラリーをしていてもほとんどその場から動かない。隣を見ると文子の脚が短いスカート(スコートというのだと後で文子に教えられた)の下からきれいに伸びている。運動神経が発達しているから動きに無駄がない。
午後の四時間ほどの練習時間が永遠に続くかと思われるほど長く、終わったときは疲れきっていた。私も格好悪いが、矢澤、亀山も酷い。矢澤は空手と間違えているのではないか。腕の動きが回転ではない。飛んでくるボールに正対してラケットを直線に動かすのだから、まともに当たる筈がない。亀山のピンポンの経験は当然のように全く役に立っていない。しきりに「おかしい」を連発する。
そんなことで始まったテニスだったが一向に上達しない。いつまでたっても私たちはコートの中を走り回り、くたびれ果てて、練習終了後のビールだけを楽しみに、むしろ苦行ともいうべきものに耐えていた。
夏になると合宿と称して二泊の旅行に誘われた。夜、食事のあとで私たちは、接待のために覚え始めたばかりの係長を無理やり誘って麻雀をしたが、あとで文子が、「こんな人たち初めてだ」ってみんなが言っていたと教えてくれる。これまでは全員でトランプをするのが食事の後の習慣だったのだそうだ。
先輩たちは練習が終わるとそそくさと帰ってしまう。大宮は遠いせいもある。せいぜい喫茶店に寄る者が数人いたが、私たちはまっすぐに居酒屋を目指す。身体が疲れているから酔いが早い。文子の少し酔った目が奇妙に色っぽい。スコートの下から覗くきれいに伸びた脚が浮かんでくる。
「俺、文子さん好き」また始まってしまった。矢澤と亀山は文子に女としての興味を感じていない。ただ愛嬌のある後輩社員としてしか見ていないから、私をけしかける。文子も嫌がっているようには見えない。飲んだ後は文子の自宅まで送っていくのが習慣になった。
しかし、私たちの趣味は決定的に違っていた。文子はガールスカウトにいたような人間だから、外で遊ぶのが好きだ。運動神経も発達していて何をやらせてもうまい。私は駄目だ。たまたま誘われて無理矢理テニスに参加しているが、本意ではない。室内にこもっているほうだから、デートの場所を選択するのでも意見が異なる。私が何か主張するわけではない。文子がお膳立てするのだが、私はあまり積極的ではない。酒を飲むことぐらいしか思いつかない。それでも私はそれなりに楽しい気分でいたが、漸く文子も気がついた。
「私たち、違いすぎるよ」と口を切ったのは文子だった。「舟木さん、いい人だけど、わたしはもっと遊びたい。発散したいんだ。」
余りにも単純で分かりやすい理屈だ。その夜はまた宮野を誘って深酒をしなければならなかった。私のテニスもこれで終わった。
|
|